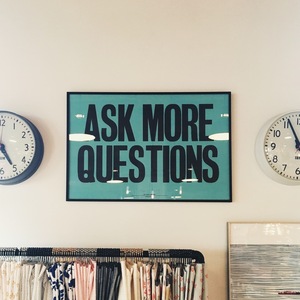【例文9選】挫折経験の書き方|就活の面接やESでの伝え方を解説
2025/11/19
目次
7.
8.
11.
「ESや面接で挫折経験を聞かれるけれど、どう答えればいいか分からない…」「答え方によってはネガティブな印象を与えてしまいそう…」そんな悩みを抱える方必見!伝え方次第で、挫折経験は自分をアピールするチャンスです。
本記事では、挫折経験がない場合の見つけ方や、面接・ESでの書き方を例文付きで紹介します。
そもそも「挫折経験」とは?
挫折とは、『仕事や計画などが途中で失敗し、だめになること。また、そのために意欲や気力を失うこと』を指します。
失敗談との違い
挫折経験とよく混同されやすいのが、失敗談です。
失敗とは、『物事をやりそこなうこと。方法や目的を誤って良い結果が得られないこと。しくじること』を指します。
辞書的な意味を比べると、「挫折」は“途中で失敗してだめになること”や“そのために意欲や気力を失うこと”を指します。一方、「失敗」は単に“うまくいかないこと”を意味します。この違いから考えると、失敗談は「物事がうまくいかなかった経験」ですが、挫折経験はその中でも特に「全力を尽くしたうえで結果が出なかった」「途中で諦めてしまった」「困難を乗り越えた」といった要素が重なる経験を指します。
就活で挫折経験を話す際は、これに加えて「挫折から得た学び」や「その学びをどう企業で生かすか」まで伝えることが大切です。
なお、企業によっては「挫折経験」と「失敗談」を混同して使う場合もあります。もし面接で「失敗談を教えてください」と聞かれたら、まずは“単なる失敗”を聞かれているのか、“失敗を通じた成長”を聞かれているのかを確認すると安心です。
挫折経験の3タイプ
挫折経験は大きく分けて3つに分類できます。
▼挫折経験の3タイプ
・モチベーションが切れて継続できなかった経験
・努力したが能力が足りず目標を達成できなかった経験
・人を巻き込んで努力したが、成果に繋がらなかった経験
モチベーションが切れて継続できなかった経験
挫折経験の1つ目として挙げられるのが「モチベーションが切れて継続できなかった経験」です。
具体的には、次のような事例が挙げられます。
具体的には、次のような事例が挙げられます。
▼モチベーションが切れて継続できなかった経験
・痩せるために夜ご飯を食べないようにしていたが、ある日夜ご飯を食べてしまったことで気持ちが切れてしまい、ダイエットを続ける意欲がなくなってしまった。
・資格勉強を始めたものの目的を見失い、途中で学習をやめてしまった。
・サークル活動で役割にやりがいを感じられず、参加意欲を失ってしまった。
努力したが能力が足りず目標を達成できなかった経験
挫折経験の2つ目として挙げられるのが「努力したが能力が足りず目標を達成できなかった経験」です。
具体的には、次のような事例が挙げられます。
具体的には、次のような事例が挙げられます。
・営業コンテストに向けて努力したが、実力が及ばず目標成績を達成できなかった。
・スポーツ大会でレギュラーを目指したが、技術不足で選考に通らなかった。
・学園祭の企画で多くの時間を費やしたが、準備不足で満足のいく結果を残せなかった。
人を巻き込んで努力したが、成果に繋がらなかった経験
挫折経験の3つ目として挙げられるのが、「人を巻き込んで努力したが、成果に繋がらなかった経験」です。
具体的には、以下のような事例が挙げられます。
▼人を巻き込んで努力したが、成果に繋がらなかった経験
・仲間と協力してイベントを企画したが、集客が思うように伸びず期待した成果を上げられなかった。
・チームでプレゼンに取り組んだが、意見がまとまらず納得のいく発表に仕上げられなかった。
・アルバイト先で業務改善を提案したが、周囲の協力を得られず実現に至らなかった。
企業が面接やESで「挫折経験」を聞く意図3選
本項では企業が面接やESで「挫折経験」を聞く3つの意図について解説していきます。
▼企業が面接やESで「挫折経験」を聞く意図3選
・自分を客観視できているかを知りたい
・挑戦意欲を知りたい
・ストレス・プレッシャーへの耐性を知りたい
自分を客観視できているかを知りたい
企業が面接やESで「挫折経験」を質問する1つ目の理由は、自分を客観的に捉えられているかを知るためです。
社会人に求められるのは、失敗から学び、同じ過ちを繰り返さない姿勢です。そのためには、自分の行動や失敗の原因を冷静に振り返り、客観的に分析して、成長へとつなげる力が必要です。
このような理由から、企業は「挫折経験」を通じて、応募者が自分を客観視し、失敗を糧に成長できる人物かを確かめているのです。
挑戦意欲を知りたい
企業が面接やESで「挫折経験」を質問する2つ目の理由は、挑戦する意欲を知るためです。
社会人に求められるのは、会社の利益や目標の達成に向けて、主体的に行動する姿勢です。そのためには、未知の領域にも果敢に挑み続ける力が必要です。
このような理由から、企業は「挫折経験」を通じて、応募者が主体的に挑戦し続けられる人物かを確かめているのです。
ストレス・プレッシャーへの耐性を知りたい
企業が面接やESで「挫折経験」を質問する3つ目の理由は、ストレスやプレッシャーへの耐性を知るためです。
社会人に求められるのは、どんな状況でも冷静に対応できる姿勢です。そのためには、ストレスやプレッシャーに押しつぶされず、状況を冷静に判断する力が求められます。
このような理由から、企業は「挫折経験」を通じて、応募者がストレスやプレッシャーがかかる場面でも落ち着いて行動できる人物かを確かめているのです。
挫折経験がない人必見!挫折経験の探し方5選
本項では、「挫折経験が思い浮かばない」「自分には挫折がない」と感じている学生に向けて、挫折経験を見つけるための5つの方法を解説します。
▼挫折経験の探し方5選
・自分史・モチベーショングラフを作成する
・全力を尽くした経験を探す
・途中で諦めた経験を探す
・過去に困難を乗り越えた経験を探す
・自分自身に質問を投げかけ分析をする
自分史・モチベーショングラフを作成する
自分史やモチベーショングラフを作成し、自分の人生を目に見える形で振り返ってみましょう。
自分史とは、これまでの出来事や当時の感情などを時系列で整理して書き出す自己分析の方法です。
モチベーショングラフとは、人生の中でのモチベーションの変化を数値化し、その時期に起こった出来事とあわせてグラフで可視化する自己分析の方法です。
このように、過去の経験を目に見える形で整理することで、自分がどのような場面で壁にぶつかり、どのような心情の変化があったのかが明確になり、挫折経験を見つけやすくなります。
自分史やモチベーショングラフの書き方やフォーマットは以下の記事を参考にしてみてください。
全力を尽くした経験を探す
自分史やモチベーショングラフで浮かび上がった経験の中から、特に自分が全力を尽くしたと思える経験を洗い出しましょう。
探す際のコツは、自分が目標に向かって最も努力していた時期や、強い達成意欲を持って取り組んでいた場面に注目することです。
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していた。
途中で諦めた経験を探す
さらに、全力を尽くした経験の中から、途中で諦めた経験を洗い出しましょう。
探す際のコツは、目標に向かって努力していたにもかかわらず、思うような成果が得られずに途中で手を止めてしまった場面を振り返ることです。
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していたが、途中で勉強をやめ、その結果、第一志望の大学に不合格という結果になってしまった。
過去に困難を乗り越えた経験を振り返る
そして、全力を尽くしたが、途中で諦めた経験の中から、困難に直面しながらも乗り越えることができた経験を洗い出しましょう。
探す際のコツは、途中でうまくいかない状況に陥ったものの、工夫や努力を重ねることで最終的に成果を出した場面や、継続することで成長を実感できた経験に注目することです。
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していたが、途中で勉強をやめてしまい、第一志望に不合格となった。しかしこの挫折を受けて勉強法を見直したことで、翌年に合格をつかみ取ることができた。
自分自身に質問を投げかけ分析する
浮かび上がってきた経験に対して「なぜ?」という疑問を繰り返し投げかけることで、自分が挫折した背景にある要因を明確にできます。
投げかける回数の目安は5回と言われています。
「全力を尽くした理由」、「途中で諦めた理由」、「困難を乗り越えることができた理由」に対して、それぞれ5回ずつ「なぜ?」という疑問を投げかけてみましょう。
1.全力を尽くした理由
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していた。
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していた。
①なぜ、難関大学に合格したいのか?
①なぜ、難関大学に合格したいのか?
→ 大企業に入りたいから
➁なぜ、大企業に入りたいのか?
→ お金持ちになりたいから
③なぜ、お金持ちになりたいのか?
→ 好きなことに挑戦できる生活を送りたいから
④なぜ、好きなことに挑戦できる生活を送りたいのか?
→ 限られた人生の中で後悔せず、やりたいことに挑戦したいから
⑤なぜ、限られた人生の中で後悔せず、やりたいことに挑戦したいのか?
→ 挑戦することで得られる経験や学びを通じて、自分や周囲の人の人生も豊かにしたいと考えているから
結論:全力を尽くした背景には「経験・学びを通じて自分や周囲の人生を豊かにしたいという動機」がある。
2.途中で諦めた理由
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していたが、途中で勉強をやめ、その結果、第一志望の大学に不合格という結果になってしまった。
①なぜ途中で勉強を諦めてしまったのか?
→ 模試でずっとE判定を取ってしまい、心が折れたから。
②なぜE判定が続くことで心が折れてしまったのか?
→ 努力しても結果が出ず、「自分には向いていない」と感じたから。
③なぜ「自分には向いていない」と感じたのか?
→ 成績が上がっていく友人と比べ、自分だけが取り残されているように思えたから。
④なぜ友人と比べてしまったのか?
→ 受験勉強を「競争」として捉えており、他人の結果が自分の価値を左右すると考えていたから。
⑤なぜ受験を「競争」として捉えていたのか?
→ 合格できる人が限られており、他人より上にいなければ成功できないという思い込みがあったから。
結論:途中で諦めてしまった背景には、「他人との比較によって自分の価値を見失ってしまったこと」がある。
3.困難を乗り越えることができた理由
例:難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していたが、途中で勉強をやめてしまい、第一志望に不合格となった。しかしこの挫折を受けて勉強法を見直したことで、翌年に合格をつかみ取ることができた。
① なぜ、不合格をきっかけに学習法を見直そうと思ったのか?
① なぜ、不合格をきっかけに学習法を見直そうと思ったのか?
→ 他人との比較で自分の価値を見失っており、このままでは成長できないと感じたから。
② なぜ、このままでは成長できないと感じたのか?
→ 毎日15時間勉強しても成果が実感できず、努力が可視化されていなかったから。
③ なぜ、努力が可視化されていなかったのか?
→ 学習の進捗や達成を記録する仕組みを作っておらず、自分の成長を確認できなかったから。
④ なぜ、学習の進捗を記録していなかったのか?
→ 目標達成ばかりに意識が向き、日々の小さな努力を評価する習慣がなかったから。
⑤ なぜ、小さな努力を評価する習慣がなかったのか?
→ 他人との比較で成果ばかりを気にしてしまい、自分の成長を意識する習慣が欠けていたから。
結論:困難を乗り越えられた背景には、「不合格をきっかけに自分の成長に焦点を当て、努力を可視化できたこと」がある。
ここから、挫折経験について以下のように整理することが出来ます。
私の挫折経験は難関大学合格に向けて毎日15時間勉強していたが、途中で勉強をやめ、その結果、第一志望の大学に不合格という結果になってしまったことだ。
その背景には、「経験・学びを通じて自分や周囲の人生を豊かにしたいという動機」のもと、全力を尽くしていたものの、「他人との比較によって自分の価値を見失ってしまったこと」が挙げられる。
しかし、この挫折をきっかけに、「毎日の学習計画を細かく立て、達成できたことを記録して努力を可視化しながら勉強法を見直したこと」で、翌年に合格をつかみ取ることができた。
Matcherで挫折経験を深堀りしてもらおう!
そんな時は、“Matcher” を活用してOB・OGの方に深堀してもらうのがおすすめです!
Matcherとは
所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。
就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?
そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由
・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!
・出身大学に関係なく、OB・OG訪問できる!
・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!
・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!
・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!
魅力的な挫折経験の書き方・伝え方
ここまで、挫折経験の定義と探し方について解説してきました。しかし、いざESに書いたり、面接で話したりするとなると、「どう伝えれば魅力的に伝わるのか」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。
そこで本項では、魅力的な挫折経験の書き方・伝え方について、具体的なポイントを解説していきます。
▼魅力的な挫折経験の書き方・伝え方
・全体像
・結論
・背景
・具体的な内容
・挫折をどう乗り越えようとしたか
・挫折経験から何を得たか
・挫折経験から得た学びを企業でどう生かすか
全体像
挫折経験を魅力的に伝えるためには、全体の構成を意識することが大切です。
基本的な流れとしては、「結論 → 背景 → 具体的な挫折内容 → 乗り越え方 → 挫折から得た学び → 学びを企業でどう生かすか」という順で書くと、論理的で読みやすい文章です。この順序で整理することで、単なる「失敗の話」ではなく、「成長や学びにつながる前向きな経験」として相手に伝わりやすくなります。
次からは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
結論
まず、これから話す挫折経験の結論について伝えます。
はじめに結論を述べることで、企業側は挫折経験全体の概要を把握したうえで、具体的な内容をスムーズに理解できます。この部分では、企業側に「もっと聞いてみたい」と思わせるような結論にすることを意識するのがポイントです。
例:私の挫折経験は、難関大学合格を目指して毎日15時間勉強していたものの、途中で気持ちが折れ、第一志望校に不合格となったことです。
背景
次に、これから話す挫折経験の背景について伝えます。
結論を述べたあとに背景を説明することで、企業側はなぜその状況に至り、どのような目的で行動していたかといった、挫折経験の前提や文脈を理解できます。この部分では、挫折経験を正しく伝えるために必要な情報―たとえば、「当時の目標・状況・取り組んでいた内容」などを簡潔に含めることがポイントです。
例:もともと「経験や学びを通じて自分や周囲の人生を豊かにしたい」という思いから○○大学を志望し、勉強に励んでいました。
具体的な内容
続いて、これから話す挫折経験の具体的な内容について伝えます。
結論・背景を踏まえたうえで具体的な内容を説明することで、企業側はどのような状況で何を感じ、どのように行動したか具体的に理解できます。この部分では、事実関係を中心に、「起こった出来事やあなたの行動を時系列で整理して伝える」ことがポイントです。
例:しかし、成績が思うように伸びず、他人との比較によって自分の価値を見失ってしまってしまいました。その結果、努力の過程を評価できず、成果だけに囚われて勉強を続ける意欲を失い、第一志望に不合格となってしまいました。
挫折をどう乗り越えようとしたか
さらに、そうした挫折経験をどのように乗り越えようとしたのかについて伝えます。
挫折の具体的な内容を説明したうえで、それをどう乗り越えようとしたのかを示すことで、企業側は困難に直面した際、どのような方法や心構えで立ち向かったか具体的に理解できます。この部分では、「問題解決に向けて取った行動や思考の変化を中心に伝える」ことがポイントです。
例:不合格をきっかけに、「他人との比較ではなく自分の成長に焦点を当てよう」と決めました。毎日の学習計画を細かく立て、達成できたことを記録して努力を可視化することで、徐々に自信を取り戻し、翌年に合格をつかみ取ることができました。
挫折経験から何を得たか
そして、これらの挫折経験から何を得たのかについて伝えます。
挫折を経験したうえで、そこから何を学び、どのように成長したかを示すことで、企業側は困難を通じてどんな価値観や考え方を身につけたか理解できます。この部分では、単なる反省ではなく、「今後に活かせる学びや成長した姿勢を明確に伝える」ことがポイントです。
例:この経験を通じて、成果よりも過程に目を向けること、他者ではなく過去の自分と比較して成長を実感することの大切さを学びました。
挫折経験から得た学びを企業でどう生かすか
最後に、挫折経験から得た学びを企業でどう生かすかについて伝えます。
挫折経験から得た学びの生かし方を具体的に示すことで、企業側は入社後どのように成長し、どのように貢献してくれるかより鮮明に理解できます。この部分では、「挫折を通じて得た学びと、企業で求められる能力・価値観とのつながりに妥当性と一貫性があるか意識する」ことがポイントです。
例:今後はこの経験を活かし、仕事でも短期的な結果だけに囚われず、過程を大切にしながら継続的に改善を重ね、チームや組織の成果に貢献できる人材を目指します。
挫折経験を添削したいならMatcher

ここまで、魅力的な挫折経験の書き方・伝え方について解説してきましたが、いざESや面接で実際に話そうとすると、不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
そんな時は、“Matcher” を活用してOB・OGの方に添削してもらうのがおすすめです!
Matcherとは
所属大学や住んでいる地域に関係なくOB・OG訪問ができるアプリです。
就職活動において、「近くに頼れる先輩がいない」「OB・OGの人にメールや電話をする勇気がない」「キャリアセンターに行くのが面倒だ」などの悩みはありませんか?
そういった人は、ぜひMatcherを活用してみてください。

Matcherをおすすめする5つの理由
・大手企業からベンチャー企業の社会人3.5万人が登録している!
・出身大学に関係なく、OB・OG訪問できる!
・住んでいる地域に関係なく、オンラインでOB・OG訪問できる!
・ワンクリックで簡単にOB・OG訪問依頼できる!!
・あなたにマッチ度が高い企業のみから特別選考スカウトが届く!!
挫折経験の例文9選
実際に挫折経験を書こうとすると、どのような内容を選べばよいのかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
そこで本項では、身近で取り組みやすい9個のテーマに分けて、挫折経験の具体例を紹介します。
▼挫折経験の例文
・部活・サークル
・アルバイト
・ゼミ
・留学
・インターンシップ
・受験
・ボランティア
・趣味・習い事
・スポーツ
①部活・サークル
私の挫折経験は、高校時代の野球部で全国大会を目指して毎朝練習に取り組んでいたものの、次第に参加者が減り、やがて自分も意欲を失ってしまったことです。
当初は「全員で努力すれば必ず結果につながる」と信じ、仲間と一体感を持って練習に励んでいました。
しかし、周囲の姿勢が変化していく中で、自分一人が頑張っても意味がないと感じ、努力の目的を見失いました。
そんな時、監督から「自分が変われば周囲も変わる」と声をかけられ、自分の行動がチームに影響を与える可能性に気づきました。
そこでまず自分が率先して練習を続け、声かけや準備を欠かさないよう努めたところ、徐々に参加者が戻り、再びチームの士気が高まりました。
この経験を通じて、他人に依存せず自ら行動する姿勢の大切さを学びました。
今後はこの主体性を生かし、周囲を巻き込みながら目標達成に向けて粘り強く取り組んでいきたいと考えています。
②アルバイト
私の挫折経験は、アルバイト先で新しく入った後輩の指導を任された際、後輩のやる気が感じられず、次第に指導への意欲を失ってしまったことです。
初めて責任のある仕事を任され、「先輩として成長したい」「信頼に応えたい」という思いから全力で取り組みました。
しかし、何度も教えても後輩が同じミスを繰り返したことで自分の教え方に自信を失い、次第に努力が報われない無力感を抱くようになりました。
そんな時、店長から「教える側が変わらなければ、教えられる側も変わらない」と声をかけられ、相手の理解度や気持ちに寄り添う姿勢の大切さに気づきました。
そこでまず相手のペースに合わせ、質問を促しながら関わったところ、後輩も少しずつ自信を持てるようになりました。
この経験から、相手の立場に立って伝えることの重要性を学びました。
今後はこの経験を生かし、相手と信頼関係を築きながらチームで成果を出していきたいです。
③学業
私の挫折経験は、資格試験の勉強中に禁止していたゲームを一度してしまったことで自己嫌悪に陥り、努力が無駄に思えて勉強への意欲を失ったことです。
将来に役立つ資格を取得し、自信をつけたいという思いから、毎日計画を立てて全力で勉強に励んでいました。
しかし、一度の誘惑に負けた自分を許せず、「完璧に続けられないなら意味がない」と極端に考えてしまい、途中で諦めてしまいました。
そんな時、友人から「努力は積み重ねで評価される」と言われ、完璧を求めすぎていた自分に気づきました。
そこで気持ちを切り替え、短時間でも机に向かうことを続けた結果、再び勉強への意欲を取り戻すことができました。
この経験から、失敗を恐れずに継続することの大切さを学びました。
今後は仕事においても、一度の失敗で立ち止まらず、改善と挑戦を重ねて成果を上げていきたいです。
④ゼミ
私の挫折経験は、ゼミで出場したプレゼン大会に向けて毎日練習を重ねていたものの、次第にメンバーの予定が合わなくなり、練習を継続する意欲を失ってしまったことです。
当初は「チーム全員で努力すれば必ず結果につながる」と信じ、優勝を目指して全力で取り組んでいました。
しかし、思うように練習ができず、次第に自分一人が頑張っても意味がないと感じるようになりました。孤独感や無力感から、努力を続ける気持ちが折れてしまいました。
そんな時、ゼミの先生から「チームの空気を変えるのはリーダーの声かけ次第だ」と助言を受け、自分からメンバーに働きかけ、意見交換の時間を設けるようにしました。
その結果、再びチーム全体の意欲が高まり、最後まで発表をやり切ることができました。
この経験から、困難な状況でも他者を巻き込みながら行動する主体性の大切さを学びました。
今後はこの学びを生かし、貴社のチームの成果最大化に貢献できる存在を目指したいです。
⑤留学
私の挫折経験は、留学前に毎日オンライン英会話で練習を重ねていたものの、現地で会話が思うように通じず、英語学習への意欲を失ってしまったことです。
将来、海外でも活躍できる人材になりたいという思いから、現地で自分の考えを正確に伝えることを目標に全力で学習に取り組んでいました。
しかし、実際の会話ではスピードや言い回しが異なり、練習の成果を感じられず、「努力しても無駄だったのでは」と落ち込みました。
その後、英語が得意な友人から「伝えようとする姿勢が大切だ」と助言を受け、完璧さよりも挑戦する姿勢を意識するようになりました。
その結果、失敗を恐れず学習を継続できるようになり、英語への意欲を取り戻しました。
この経験から、失敗を恐れず継続することの重要性を学びました。
今後は貴社でも困難に直面した際、結果だけでなく過程を大切にし、粘り強く取り組む姿勢を発揮していきたいです。
⑥インターンシップ
私の挫折経験は、インターンシップでのチーム発表において、チーム全体の進捗管理が不十分で提出直前に資料の矛盾が発覚し、修正作業に追われてチームに迷惑をかけてしまったことです。
プロジェクトを成功させ、チームメンバーや社員の方から評価されたいという思いから、全力で資料作成や分析に取り組みました。
しかし、自分の担当部分に集中するあまり、チーム全体の状況を把握できず、進捗の遅れに気づくのが遅れてしまいました。
その後、完璧に自分の作業をこなすだけではチームに貢献できないことに気づき、グループワークでは定期的に進捗確認を行い、メンバーと情報を共有しながら作業を進める方法に切り替えました。
その結果、次のインターンシップでは最も優れた発表に選ばれることができました。
この経験から、チーム全体を俯瞰して調整する重要性を学びました。
今後は、貴社においてもチームの状況を把握し、主体的にコミュニケーションを取りながら成果を最大化できるよう努めていきたいです。
⑦受験
私の挫折経験は、難関大学合格を目指して毎日15時間勉強していたものの、途中で気持ちが折れ、第一志望校に不合格となったことです。
もともと「経験や学びを通じて自分や周囲の人生を豊かにしたい」という思いから全力で努力していましたが、成績が思うように伸びず、他人との比較によって自分の価値を見失ってしまったことが挫折の要因でした。
その結果、努力の過程を評価できず、「成果だけ」に囚われて勉強を続ける意欲を失いました。
不合格をきっかけに、「他人との比較ではなく、自分の成長に焦点を当てよう」と決めました。そこで、毎日の学習計画を細かく立て、達成できたことを記録することで、自分の努力を可視化し、徐々に自信を取り戻し、翌年に合格をつかみ取ることができました。
この経験を通じて、成果よりも過程に目を向けること、他者ではなく過去の自分と比較して成長を実感することの大切さを学びました。
以降は、目標を「達成」よりも「成長の積み重ね」と捉えるようにし、モチベーションを維持できるようになりました。
今後はこの経験を活かし、仕事でも短期的な結果だけに囚われず、過程を大切にしながら継続的に改善を重ね、チームや組織の成果に貢献できる人材を目指します。
⑧ボランティア
私の挫折経験は、地域の子ども向け学習支援ボランティアで活動していた際、指導した子どもがなかなか学習に集中できず、思うように成果が出なかったことです。
子どもたちの学力向上に貢献し、「将来の可能性を広げる手助けをしたい」という思いから、教材作成や指導計画の作成に全力で取り組みました。
しかし、指導方法が一方的になりすぎた結果、子どもたちの反応や理解度を十分に把握できず、焦りや無力感を感じてしまいました。
その後、先輩ボランティアから「まず子どもたちの目線に立ち、関心を引くことが大切」と助言を受け、学習内容をゲーム形式に変えたり、質問の機会を増やすなど工夫しました。
その結果、少しずつ子どもたちが集中し、学習意欲を示すようになりました。
この経験から、相手の立場に立ち、柔軟に対応することの重要性を学びました。
今後は、仕事においてもチームメンバーや顧客の状況に応じて適切に対応し、成果を最大化できるよう努めていきたいです。
⑨趣味・習い事
私の挫折経験は、ピアノの習い事で発表会に向けて練習を重ねていたものの、本番で緊張して演奏がうまくいかず、悔しさから一時的に練習への意欲を失ったことです。
ピアノ演奏を通して表現力を高め、自分自身の成長を感じたいという思いから、毎日計画を立てて練習に取り組んでいました。
しかし、練習通りに弾けなかった本番の経験から「自分には才能がないのでは」と感じ、モチベーションが下がってしまいました。
その後、先生から「失敗を恐れず挑戦することが上達につながる」と助言を受け、目標を小さな課題に分けて練習する方法に切り替えました。
その結果、練習を積み重ねるうちに少しずつ自信が戻り、次の発表会では緊張しながらも納得のいく演奏を披露できました。
この経験から、挑戦を続けることの大切さや失敗から学ぶ姿勢を学びました。
今後は、仕事においても困難な課題に直面しても諦めず改善を重ね、成果を出す姿勢を大切にしていきたいです。
⑨スポーツ
私の挫折経験は、マラソン大会に向けて毎日ランニングを続けていたものの、目標タイムを大幅に下回る結果に終わり、練習への意欲を失ってしまったことです。
自己ベストを更新し、「自分の努力で成長を実感したい」という思いから、毎朝早起きして走り込みやフォーム改善に全力で取り組んでいました。
しかし、本番では緊張や体調の変化により計画通り走ることができずに、「これまでの努力は無駄だったのでは」と落ち込んでしまいました。
その後、経験者の友人から「一度の結果で判断せず、継続することが大切」と助言を受け、練習方法を見直し、体調管理やペース配分に工夫を加えるようにしました。
その結果、次の大会では自己ベストを更新することができました。
この経験から、失敗を恐れず継続し改善を重ねることの重要性を学びました。
今後は、仕事においても困難に直面しても諦めず改善を重ね、成果を出す姿勢を大切にしていきたいです。
NGエピソード3選とその理由
ここまで、挫折経験の具体例を身近で取り組みやすい9個のテーマに分けて解説してきました。しかし、面接やESで使わないほうが望ましいエピソードも存在します。
本項では面接やESで使わないほうが望ましいエピソード3選とその理由について解説します。
▼NGエピソード3選
・ただ諦めてしまっただけの内容
・感情中心で論理的な学びが見えない内容
・不適切・個人的な内容
ただ諦めてしまっただけ内容
1つ目は、「ただ諦めてしまっただけの内容」です。
例えば、「資格試験の勉強を続けていたが、一度サボってしまったことで心が折れてしまった」という内容では、自分の成長や学びを示すことができず、面接やESでの評価につながりません。
そのため、面接やESで挫折経験を伝える際は、単に「諦めてしまった」と述べるのではなく、例えば「資格試験の勉強で一度計画通りに進められなかった原因を分析し、学習スケジュールを見直して習慣を取り戻した」というように、失敗の原因やその後の行動を具体的に伝えることが重要です。
感情中心で論理的な学びが見えない内容
2つ目は、「感情中心で論理的な学びが見えない内容」です。
例えば、「プレゼン大会で負けて悔しかった」という内容では、企業に感情は伝わるものの、そこから何を学び、次にどう改善したのかが不明瞭であり、面接やESでの評価につながりません。
そのため、面接やESで挫折経験を伝える際は、単に「悔しかった」と伝えるのではなく、例えば「資料の準備不足が原因で質問に答えられなかった」「次回は事前に想定質問を整理し、練習を重ねることで改善した」というように、原因・行動・学びの流れを具体的に伝えることが重要です。
不適切・個人的すぎる内容
3つ目に避けるべきなのは、「不適切・個人的すぎる内容」です。
例えば、「好きな人と付き合うために自分磨きを頑張ってきたが、振られてしまったことで心が折れてしまった」という内容は、恋愛という個人的なテーマであり、努力や成長が仕事や社会人としての資質に直結しないため、企業に共感されにくく、面接やESでの評価につながりません。
そのため、面接やESで挫折経験を話す際は、挫折経験の例文9選のような社会人としての資質や成長がイメージできる内容を選ぶことが重要です。
挫折経験がどうしても見つからなかった場合の対処法
挫折経験がどうしても見つからなかった場合は、無理に作る必要はありません。
本項では、「挫折経験がどうしても見つからなかった場合の対処法」と「挫折経験がどうしても見つけられなかった場合の例文」についてご紹介します。
挫折経験がどうしても見つけられなかった場合の答え方
結論からいうと、「挫折経験がない」と正直に答えても問題ありません。ただし、答え方には工夫が必要です。
挫折経験がどうしても見つからなかった場合は、挫折をしないためにどのような対策を講じてきたか具体的に伝えることで、企業に前向きな姿勢や自己管理能力をアピールできます。
挫折経験がどうしても見つけられなかった場合の例文
▼挫折経験がどうしても見つけられなかった場合の例文
私はこれまで大きな挫折を経験したことはありません。
常に入念な準備を重ね、困難に直面する前に対策を講じることで、計画通りに物事を進めることが多かったためです。
たとえば大学受験の際も、早い段階から過去問分析や学習計画の立案を行い、模試ごとに弱点を洗い出して修正を重ねることで、焦ることなく本番を迎えることができました。
また、ゼミ活動やアルバイトでも、トラブルが起こる前にメンバー間のスケジュール共有やタスク管理を徹底することで、大きな問題を未然に防いできました。
もちろん、今後の社会人生活では予期せぬ困難や失敗もあると思います。そうした状況でも、これまで培ってきた計画性と冷静な分析
力を生かし、原因を見極め、改善策を講じながら粘り強く取り組む姿勢で臨みたいと考えています。
まとめ
本記事を通して、1人でも多くの方が自分の挫折経験を整理し、面接やESで自信を持って伝えられるようになることを願っています。
挫折経験の有無にかかわらず、自己分析を深め、困難にどう向き合ったかを具体的に示すことが、企業に対して前向きで成長意欲のある人物であることを印象づける鍵です。
ぜひ、本記事で得た考え方や具体例を参考に、自分らしい挫折経験の伝え方を身につけてください。