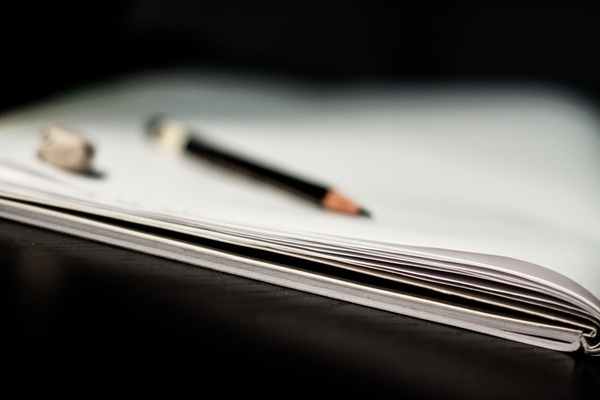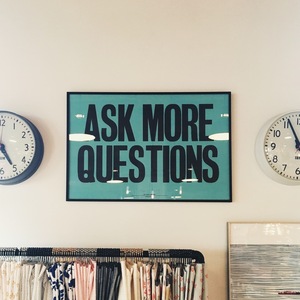【超簡単】就活の軸を的確に設定するための方法や例文一覧をご紹介
2023/09/25
目次
1.
「就活におけるあなたの軸を教えてください」というのはESや面接などの選考過程で聞かれる定番質問のひとつです。
とはいえ、「とにかく幅広く企業を見てるから軸なんてないし…」「なんで就活の軸を答えなきゃいけないの?」と悩んでしまう方も多いことも事実。そこで、この記事は就活の軸を誰でも簡単に、的確に設定するための方法をご紹介していきます。
✩この記事のオススメポイント
-「就活の軸」とは何かが分かる
- 自分にぴったりな「就活の軸」の見つけ方が分かる
- 業界/職種別で見る「就活の軸」例文が読める
- 「就活の軸」から企業は何を評価しているのか
就活の軸が決められない、自分にぴったりな就活の軸が分からないといったお悩みをお持ちの場合、ぜひこの記事を参考にしてみてください!
▼関連記事
「就活の軸」とは?
就活の軸に関して質問されることは多々ありますが、そもそも就活における「軸」とは何なのでしょうか?
就活の軸とはすなわち、自分が働くにあたって絶対に譲りたくない要素のことです。
ここでは「就活の軸」を構成する表と裏の要素や、企業が「就活の軸」を選考過程で聞く意図について詳しく紹介していきます。
就活の軸には表と裏がある
「就活の軸」を決める際は、志望企業を決めるための「本音の就活の軸」と、選考で聞かれた場合に答える「表向きの就活の軸」の2つを考える必要があります。
本音の「就活の軸」
「高給与の仕事に就きたい」「仕事中心の生活は嫌だ」といった本音で構成された就活の軸は、自分が本当に行きたい企業を見つけるために設定しましょう。
このような「本音の軸」は自分の欲望や会社に対しての要望なので、面接やESに書いてしまうと悪印象を与える可能性が非常に高いです。一方で、企業選びの際に「本音の軸」を意識することは、自分との相性が良い企業を見つけるために欠かせません。
▼本音の「就活の軸」例
・20代で年収1000万円を実現できる
・残業時間が月15時間未満
・福利厚生が充実している
・有名人と会う機会の多いところで働きたい
ESや面接で使う「就活の軸」
企業に対する自分の要求が含まれる「本音の軸」に対して、ESや面接で使う「就活の軸」には企業への自己アピールの要素が含まれます。
「自分の将来の目標/キャリアプランは何か?」「自分が社会にどのように貢献したいのか?」といった内容を盛り込み、「就活の軸」を通して自分の人柄や思考などを面接官に訴求します。
▼ESや面接で使う「就活の軸」例
・地域に密着し、金融の面から人々の暮らしをサポートできる
・IT技術によって人々の生活を豊かにできる
・企業課題の解決に取り組み、日本経済を豊かにしたい
・食の面から人々の健康を支えたい
就活の軸をESや面接で聞かれる意図
なぜ企業が選考過程において「就活の軸」を聞くのだろうと疑問に思ったことがある方もいるのではないでしょうか。
企業は「学生に内定を出したとして、承諾してもらえるのか?」「研修にかかるコストを割いたにも関わらず、すぐに辞めてしまわないか?」といった疑問を解決するために、「就活の軸」についての質問項目を設けています。
「就活の軸」について質問された時は、企業への志望度やマッチ度を測られていると思ってよいでしょう。
就活の軸に悩んでいるならMatcherがオススメ
「就活の軸」には正解がありません。だからこそ「就活の軸をどうやって決めたらいいかわからない」「とりあえず決めても、これでいいのか分からない」と悩んでしまいますよね。
そこでオススメしたいのが、就活に関するお悩みを社会人や内定者に相談ができるOB・OG訪問サービスのMatcher(マッチャー)です。
▼OB・OG訪問サービス Matcherの活用例
・就活の軸を一緒に考えてもらう
・就活初期にやっておくべきことについて教えてもらう
・ES添削をしてもらう
・面接対策をしてもらう
就活を経験し、乗り越えてきた経験者に相談することは、納得のいく就職活動に繋がります。自分に合った就活の軸を見つける際は、ぜひMatcherを活用してみてください!
就活の軸を見つける3つの視点
就活の軸は、以下の3つの視点から見つけることができます。▼就活の軸を見つける3つの視点
興味・関心:どういう仕事がしたいか?
働く人・カルチャー:どういう環境で働きたいか?
強み・適性:どういう業務が自分の長所を活かせるか?
それぞれ詳しく解説していきます。
興味・関心
志望業界などは「食が好きだから」「最新技術に興味があるから」といった興味や関心で決める学生さんも多いです。
一方で、説得力のある就活の軸にするためには、そのものに興味や関心がある理由を論理立てて説明していくことが必要です。自分の興味や関心に繋がるエピソードを見つけるためにも、自己分析や他己分析を行うことをオススメします。
自己分析・他己分析から就活の軸を見つける
例えば「人をあっと驚かせることが好き」という興味が「調理部で隠し味を研究していた経験」から説明できるかもしれません。
自分史を書いてみたり、モチベーショングラフを書いてみたり、自分自身で過去を振り返ることで、興味や関心が強い対象と理由を見つけることができるでしょう。
また、他己分析を通して別の視点から自分自身について知ってみることもオススメです。
▼関連記事
働く人・カルチャー
実際にその企業で働いている人や社内の雰囲気を見て「自分に合っているな」と思うこともあるでしょう。
例えば「出る杭を打たずに伸ばしていく環境」「上下関係がフラットなカルチャー」などを就活の軸として置くこともできます。
とはいえこの就活の軸を見つけるためには、実際に企業へ訪問したり、社員の人に会ったりする必要があります。働く人・カルチャーの面から就活の軸を見つけるためには、会社説明会やOB・OG訪問を行いましょう。
会社説明会から就活の軸を見つける
会社説明会では、事業内容の他に、求める人物像や社内のカルチャーなども紹介されることが多いです。求める人物像からは、社員の性格や特徴を見ることができます。
オンラインではなく対面の会社説明会の場合は、会社の中の雰囲気も体感することが可能です。就活の軸として話せるように、出会った社員さんの印象や、話した会話の内容などを覚えておくことがオススメです。
会社説明会の他にも、企業主催の座談会や短期インターンも、短い時間で企業の雰囲気を体験できます。機会を見つけたらぜひ参加してみてください。
OB・OG訪問から就活の軸を見つける
志望する企業に所属する社員と1対1でしっかりと話すことができるOB・OG訪問は、働く人やカルチャーを知る上で欠かせません。
OB・OG訪問をした経験がある学生のうち、会った人数は24年卒の平均で4.9人です。気になる企業を見つけたら、ぜひ話を聞きに行ってみてください。
【参考】マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査『5月の活動状況』
【参考】マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査『5月の活動状況』
「今までOB訪問したことがないから、どうすればいいか分からない」「どうやってOB訪問する社会人と知り合えばいいんだろう」という就活初心者の方でも安心なOB・OG訪問サービスMatcherでは、社会人や内定者が提示するプランの中から気になるものを見つけ、ボタンを押すだけで日程調整まで進むことができます!

就活の軸をOB・OG訪問を通して見つけたい方は、ぜひこちらから登録してみてください。
MatcherでOB訪問できる相手を探してみる(無料)
強み・適性
自分の強みや特性から逆算して、就活の軸を見つけることができます。
例えば「負けず嫌いな努力家」という強みがあるならば、「実力評価主義の環境」であることを就活の軸として設定することが可能です。
このような強みや特性は、今までの経験から見つけると、具体性を持った説得力のある就活の軸になるでしょう。面接やESなどで就活の軸を聞かれた場合は、強みや適性から逆算したものを答えることがオススメです。
以下で、アルバイト経験、長期インターンシップ経験、スポーツ経験から就活の軸を見つける例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
アルバイト経験から就活の軸を見つける
アルバイト経験における自分が頑張ったことや意識したこと、挙げた成果などから就活の軸を見つけられます。
以下では「塾講師」のアルバイトで、「責任のある仕事を与えられたこと」によって自分の力を伸ばすことができた経験から「若いうちから裁量権の大きい仕事ができる」という就活の軸を見つけた例文を書きました。
▼アルバイト経験から就活の軸を語る例文
私の就活の軸は「若い時から自分の役割が与えられ仕事を任せられること」です。
私は学生時代、塾講師のアルバイトをしていた際に、バイトを始めたばかりなのに責任のある仕事を任せてもらったことにやりがいを感じました。実際に、生徒の性格や目標に沿って、一人一人に合った指導や対策を自分で考えて指導を行いました。私は、生徒の苦手分野や集中力の持続性などに着眼し、それを改善できるように勤めました。
さらに、生徒のモチベーションを維持するために、「良い結果を残せた時にはしっかりと褒める」「生徒が納得できるように、言葉だけではなく図を使って指導する」といったように意識的に行いました。その結果、担当した生徒のうち約8割ほどの生徒の学力を伸ばすことができました。私は、生徒一人一人に向き合い成長させていくことで、自分で判断して課題を解決することにもやりがいをとても感じるようになりました。
説明会やOB訪問を通して、貴社の社員の方が主体的に責任を持って言動している点に強く共感し、魅力を感じました。
長期インターンシップ経験から就活の軸を見つける
長期インターンシップ経験は、実際に志望する業界で働くイメージがわきやすいため、就活の軸が見つかりやすいです。
以下では「IT企業」での長期インターンで、「ITと金融の繋がりを実感した」ことによって「どちらの業界にも携われる会社で働きたい」という就活の軸を見つけた例文を書きました。
▼長期インターンシップ経験から就活の軸を語る例文
私の軸は、「テクノロジーをを用いることで金融業界に影響を与える」ことです。
私は、商学部に所属し、ゼミで金融論について研究しています。経済の中でお金はなくてはならない存在です。人が生きていく上でも、企業を経営する上でも、お金は絶対必須です。その中で、金融論について学ぶに連れてとても金融に強い関心を持ちました。
私は、IT企業の長期インターンで企業向けにシステムの営業を行う上で、ITやシステムが企業の歯車となり、変革していくという実感が湧きました。
デジタル社会のなかで、金融とお金の関係のように現代社会においてIT企業は不可欠であると感じ、興味を持ち始めました。その結果、インターンをやっていて、ITシステムの大切さを知り、金融とITは切っても切り離せない関係であると感じ、その二つの業界に携われる会社で働きたいと感じました。私は、生活のインフラである金融業界の変革を支えるIT企業を志望します。
スポーツ経験から就活の軸を見つける
部活動などにおけるスポーツ経験からは、組織の中で自分が活躍できる役割や環境などを見つけることができます。
以下では「野球」の部活動で、「練習メニューの改善案を提案・実行した」経験から「今までの当たり前に囚われずに、新しいイノベーションを起こす」という就活の軸を見つけた例文を書きました。
▼スポーツ経験から就活の軸を語る例文
私の軸は、「イノベーションや新規事業に重きをおく企業に就職すること」です。貴社では、業界の常識にとらわれず、新しい市場を作り出すことや参画することが重視されています。
私は、小学校から野球を初め、そのまま、大学でも体育会野球部に入部し、部長を任されました。練習では、ストレッチや準備運動が全体と比較すると少なく、走りこむことが多かったです。そのため、足や膝に常に負担がかかり怪我をしてしまう学生は多くなかったです。
そこで私は、野球に必要な筋肉を重点的にできるトレーニングやケアの重要性を発信し、練習の内容を変える提案をしたところ、コーチには走り込むことで基礎的な体づくりもできると考えていたため、反対されました。しかし、根拠あるデータや実例をあげつつ、熱意を伝えることで、最終的には練習メニューの改善案が認められるようになりました。
このような取り組みを行なった結果、国公立戦で入賞を果たすことができました。私は、この経験を踏まえて、それまで当たり前だった常識や決められていることに対して課題点を発見して、それを改善して最終的に成果に繋げるやりがいを感じることができました。貴社でも、今までの業界の常識や当たり前であることに囚われずに、新しい提案をしていきたいです。
例文一覧|業界・職種別「就活の軸」
ここでは、業界ごとの「就活の軸」例についてご紹介していきます。以下の業界ごとに例をまとめています。
-IT業界
-金融業界
-食品メーカー
-コンサルティング
-不動産業界
-人材業界
-総合職(営業)
-総合職(マーケティング)
-事務職
IT業界の例
まずはIT業界の例についてみていきます。
新しい技術やサービスを開発したい
IT業界は、急速に変化し成長を遂げました。そのため、変動するなかでもスピード力は衰えません。
自分が世の中のニーズに答えて、積極的に新しい技術やサービスを提供したい熱意を伝えると良いでしょう。
独立に興味がある
IT業界は「個の力」も不可欠です。「個の力」つまり、独立心の強さも求められる要素の1つです。
一方で「数年後にベンチャーで働きたい」「独立したい」という意志は、人事からは悪印象を与えてしまう可能性が非常に高いです。
というのも人事側では、長く働いてくれる人材を求める傾向があるからです。そのため、「社内ベンチャー」と表現することで、独立心を主張しながら、企業に長く務めるという意志をアピールできます。
エキスパートと共にプロジェクトを遂行したい
IT業界では、専門的な知識やスキルを持つ人たちと共にプロジェクトを行う「プロジェクト型」が多いため、エキスパートと共にプロジェクトを遂行することができます。
そのため自分自身も周りに影響を受けながら成長したいという意志をアピールすることができます。
金融業界の例
続いて、金融業界の軸の例について紹介していきます。
人の助けになる支援・応援を行いたい
金融業界では、お金を融通して人を助けます。銀行であれば、人を助けるための事業を応援することや保険であれば安心を提供することができます。人の助けをしたいという方には、おすすめの「就活の軸」です。
責任の大きい仕事がしたい
人を助けるからには責任というものも生まれます。さらには、周りからお金を集めるため、一緒に応援する人たちに対しても責任が高まります。
責任感ある仕事をして成長したい方は、金融業界で「責任感ある仕事をしたい」という軸を起用することをおすすめします。
裁量があり、その成果を見られる風土の会社に努めたい
金融業界、金融機関によっては、業務に対してシビアに評価を与えられます。そのため、他業界とは異なり、著しく給与や昇進があります。
自分がコミットし、成果をだしたぶん報酬が変動します。自身のスキルや強みを生かして、その成績に応じて役割を与えられるような環境で成長したい方にはぜひ参考にして欲しいです。
食品メーカーの例
続いて食品メーカーの就活の軸の例を見ていきます。
周囲を巻き込んだり、多くの人と携わって仕事がしたい
食品メーカーでは、新商品企画から商品がお客様の手に届くまでの工程が山ほどあります。たくさんの人を巻き込んでいくことで商品が出来上がってきます。そのため、「多くのメンバーと連携をとりたい」と軸を定める人は多いです。
人々の健康を支え、感動を与えたい
「安全でヘルシーな食品」を生産することで、日本だけでなく海外に住む人々にも届けることができます。食から健康をサポートすることは、多くの人が実践しているため、たくさんの人々を支えることが可能です。
また、食を通して感動を与えたい人もいれば、見栄えや美しさで感動を与えたい人がいます。それに対して、食品メーカーでは、食を通して言えば、商品の成分や食材、見栄えや美しさで言えば、パッケージや店舗で感動を与えることができます。
責任感を持ちながら、やりがいがある仕事をしたい
食品メーカーでは、商品が出来上がる過程が多いと同様に、安全性や生産管理など重要な審査もクリアしていかなければなりません。さらに、法律上にも関わる規定もあるため、一つ一つの過程に責任感を持たなければなりません。
そのため、多くの山場がある分、とてもやりがいを感じることができます。
コンサルティング業界の例
続いてコンサルティング業界の例について紹介していきます。
幅広く課題を解決していきたい
コンサルティングの顧客の抱える課題は、企業によって異なるため、多種多様な課題に対応しなければなりません。そのため、幅広く課題に対して解決することが強みの方は、「就活の軸」にすると効果が期待できます。
様々な事業・業界を知りたい
幅広い課題により、事業内容や業界を超えて業務を行うことが多いです。課題の解決案次第によっては、全く異なる業界に参入することもあります。
「一つの業界だけでなく超越していくこと」を軸にすることができます。
業界・業種を超えて色々な方々と携わりたい
上記同様に、他業界に参画することで異なる業種の人とも携わります。人との信頼を築くためのコミュニケーション能力などが高いことで、融通が効きやすく円滑にプロジェクトを遂行できます。コミュニケーションや多くの人と携わることを主張した「就活の軸」は、作りやすいです。
不動産業界の例
続いて不動産業界の就活の軸の例について紹介していきます。
街づくりがしたい
不動産業界で、デベロッパーという役職についた場合、主に「六本木ヒルズ」や「アクアシティお台場」など、商業施設の都市開発に携わることになります。
そのため、プロジェクトを遂行していく中で、街の変化や人が集まるような施設を創り出すことで最終的に街づくりをすることができます。
目標・目的を持って仕事に取り組みたい
不動産業界では、長期的ビジョンを目標に掲げ業務を行なっていく場合と、住居の手配に関して、数ヶ月から半年のスパンで業務を行い最終的にお客様が快適にスムーズに入居することを目標として掲げています。
そのため、どの業務に対しても高い目標を持って、最大の成果になるように業務を行うため、目標や目的があって仕事をしたい人にはアピールポイントになります。
人生の転機となる瞬間に立ち会いたい
不動産は、人生のなかでも非常に高額な買い物なため、人の重大な転機に立ち合うことができます。
そのため、不動産業界には人の転機となる瞬間に立ち会いたいと考える人が多くいます。
人材業界の例
続いて人材業界の就活の軸の例を紹介していきます。
人の役に立ちたい
人材業界では、人と会社を繋ぐ仲介者の立場です。人と会社の方々のために人材を教育、育成する業務などを行います。そのため「人と真摯に向き合える人材」を求めています。
人の成長を応援したい
人材を教育、育成するのが大きな業務です。そのため、その人が成長していく姿を見守ったり、教えたりすることが非常に多いです。
人に対して素直に応援できる人材が、人材業界で大きな役割を担います。
正解が決まっていない仕事をしたい
人との関わりが多種多様であり、その人に応じてサポートしていきます。また、企業によっても求める人材も異なっていくため、一人一人のサポートも企業に対する取り組みも正解がないため、自分自身で考えて答えを導きます。
総合職(営業)の例
続いて職種別にみていきます。
まずは総合職の場合の就活の軸の例です。
まずは総合職の場合の就活の軸の例です。
事業に対して最前線で取り組みたい
総合職は、幹部候補となる可能性があります。さらに営業職は、売り上げにおいて、牽引していくポジションです。
事業に対して、貢献していきたいことは一つの就活の軸になります。
結果が数字に表れる仕事をしたい
営業職は、数字が命というように数字で動きます。目標や実績、達成率、自分の行動に対して、全てを計算して把握します。
そのため、数字が目標とそれを達成する力が必要です。
目標達成することを主軸に考えると、自分の就活の軸を見つけるきっかけになるでしょう。
目標達成することを主軸に考えると、自分の就活の軸を見つけるきっかけになるでしょう。
コミュニケーションをとって行う仕事をしたい
営業職は、コミュニケーションが必要不可欠です。
コミュニケーションをとって、お客様に商品の良さをお伝えします。
この場合は、就活の軸として、コミュニケーション能力ベースで書くことがおすすめです。
総合職(マーケティング)の例
続いて総合職(マーケティング職)の場合の軸の例について見ていきます。
新しい考えやアプローチをしたい
ブランドや製品を世の中に広めていくお仕事がマーケティング職の醍醐味です。今までとは違う拡散方法やアプローチをしていきます。
新しいことを考えたり、試行錯誤を地道にできる人材が求められています。そのため、考えることが好きな方はぜひそのまま軸として組み立てて欲しいです。
論理的に考える仕事に就きたい
マーケティング職では、過去のデータから仮説をとり、実際に実行してみるというのが手順になっていきます。
そのため、分析力などが重視されるため論理的に考えることがとても重要になります。
最先端なもの、最新技術やサービスを作り出したい
ブランド、製品価値を高めるためには、周りとの差別化も必要になります。また、変動する市場についていく必要があります。
最先端なもの、最新技術やサービスに敏感であり、作り出していくことが重要です。
事務職の例
最後に事務職の就活の軸の例について見ていきます。
長く働きたい
「長く働きたい」というと待遇がいいからそのように聞こえてしまう一方で、事務職という、社内の手続きや調整が必要な業務では、長く勤めてもらうことがとても重要なため、企業に悪印象を与えることはないです。
実際に落ち着いていて、常に調節し、長く働いてくれる人が多く活躍されています。
組織をバックサポートしていきたい
組織に直接入って、牽引するのではなく、その組織にいる方々にとって働きやすい環境を整えてくれるのが事務職です。
組織に率先して所属している人たちが最大のパフォーマンスができるようにサポートしていきます。
ワークライフバランスを重視したい
事務職は、残業することが多くないため自分の生活とのバランスも取れます。
長く勤めて欲しいという人材を求めている中で、自分の生活をも重視することで長く勤められる一つの要素になります。
企業に就活の軸を伝えるときのポイント
就活の軸を伝えるときは、やりがいを感じられる仕事を、その企業で叶えられることを伝えることが大切だと述べました。では、どのようなことを意識すれば、就活の軸に説得力が出るのでしょうか?
ここでは3つのステップに分けて、就活の軸を考える上でのポイントを説明します。
業界研究・企業研究を通して、その企業でどのような仕事がしているのか理解するようにしてください。 仕事のことについて知るには、OB訪問もおすすめです。業界研究や企業研究とは異なり、仕事のやりがいや苦労など、現場に根ざした話を聞くことができるからです。 OB訪問をするのにおすすめなのが、OB訪問のマッチングサービス、Matcher(マッチャー)。
所属大学や学年に関係なく、気になる企業の社会人に話を聞きに行くことができます。
 【社会人の所属企業例(一部)】
三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、みずほ銀行、三井住友銀行、マッキンゼー、リクルート、電通、博報堂、日産自動車、日本テレビなど5000社
【社会人の所属企業例(一部)】
三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、みずほ銀行、三井住友銀行、マッキンゼー、リクルート、電通、博報堂、日産自動車、日本テレビなど5000社
社会人に掛け値なしにお願いできるのは、大学生であるこの時期だけ。ぜひ社会人に会いに行って、就活の糧にしてください。
ここでは3つのステップに分けて、就活の軸を考える上でのポイントを説明します。
①選考を受ける企業と業界について調べる
自分の志向性と企業で働くことがマッチしていることを伝えるためには、そもそも企業がどのような仕事をしているのかを知らなければなりません。
業界研究・企業研究を通して、その企業でどのような仕事がしているのか理解するようにしてください。 仕事のことについて知るには、OB訪問もおすすめです。業界研究や企業研究とは異なり、仕事のやりがいや苦労など、現場に根ざした話を聞くことができるからです。 OB訪問をするのにおすすめなのが、OB訪問のマッチングサービス、Matcher(マッチャー)。
所属大学や学年に関係なく、気になる企業の社会人に話を聞きに行くことができます。
 【社会人の所属企業例(一部)】
三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、みずほ銀行、三井住友銀行、マッキンゼー、リクルート、電通、博報堂、日産自動車、日本テレビなど5000社
【社会人の所属企業例(一部)】
三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、みずほ銀行、三井住友銀行、マッキンゼー、リクルート、電通、博報堂、日産自動車、日本テレビなど5000社社会人に掛け値なしにお願いできるのは、大学生であるこの時期だけ。ぜひ社会人に会いに行って、就活の糧にしてください。
Matcherに登録する(無料)
次は、なぜその仕事をしたいのかを説明できる状態にします。このときに大切なのが、過去の自分の経験を踏まえて説明できるようにすることです。 ただ「この仕事したい!」と声高に主張しても、説得力がありません。その仕事がしたいと思うに至るまでにどのような経験をしてきたのかを伝えられて初めて納得してもらうことができます。 ①自分の就活の軸は〇〇ができることです。 ②私は今までに☓☓の経験をし、その経験から〇〇にやりがいを感じるようになりました。 ③就活では、〇〇ができる△△業界や■■業界を見ています。 実際にESや面接で就活の軸を聞かれた場合は上記のような流れにするのがおすすめ。これによって説得力を持った就活の軸を伝えることができるとともに、選考を受けている企業の業界を志望する理由も説明することができます。
②なぜその企業なのか、自分の経験を踏まえて話せるようにする
業界研究や企業研究、OB訪問を通して仕事のことを知りました。
次は、なぜその仕事をしたいのかを説明できる状態にします。このときに大切なのが、過去の自分の経験を踏まえて説明できるようにすることです。 ただ「この仕事したい!」と声高に主張しても、説得力がありません。その仕事がしたいと思うに至るまでにどのような経験をしてきたのかを伝えられて初めて納得してもらうことができます。 ①自分の就活の軸は〇〇ができることです。 ②私は今までに☓☓の経験をし、その経験から〇〇にやりがいを感じるようになりました。 ③就活では、〇〇ができる△△業界や■■業界を見ています。 実際にESや面接で就活の軸を聞かれた場合は上記のような流れにするのがおすすめ。これによって説得力を持った就活の軸を伝えることができるとともに、選考を受けている企業の業界を志望する理由も説明することができます。
就活の軸を作るとどんなメリットがあるの?
これまでは就活の軸の作り方と、その具体例を紹介してきました。 ではそもそもなぜ就活の軸は作らなければならないのでしょうか。 ここでは就活の軸を作るメリットについて、紹介していきます。 大きく分けて以下の3つのメリットがあるとされています。 ①受ける企業・業界を絞るのに役立つ ②面接の内容に一貫性がでる ③将来ビジョンが明確になる 1つずつ具体的に見ていきましょう。メリット1:受ける企業・業界を絞るのに役立つ
まず1つ目のメリットとして挙げられるのが「企業選びの判断基準が確定できる」ことです。
将来ビジョンを明確にするためにも、就活の軸の作成は重要です。
多くの就活生は「過去の経験」と「将来ビジョン」の2つの側面から、就活の軸を決めるでしょう。
例えば「日本が抱える社会問題を解決したい」「ITスキルが活かせる仕事に就きたい」といった軸は、過去の経験と将来やりたいことの両側面から決められた軸といえます。
「何となく就活をやっていた」という人でも、就活の軸を決めることによって、今よりも将来ビジョンが明確になるはずです。 就職活動で人生は終わりません。むしろ就職してからが本番です。
「内定を取るためにどうしたらよいか」だけを考えるのではなく「自分が本当にやりたいことは何か」を真剣に考えることによって、就活の軸にとどまらない「本当の将来ビジョン」が明確になるでしょう。
大学生である皆さんは、「業界・会社が多すぎて、どこに自分がマッチするのかわからない・・・」と悩んでいる方も少なくないはずです。
そんな悩みを解決できるのが「就活の軸」を決めることです。
・WEBに関わる仕事がしたい
・法人営業がしたい
・人と頻繁に関わる仕事がしたい
など、就活の軸を複数個定めておくことで、企業・業界をより絞りやすくなるでしょう。
メリット2:面接の内容に一貫性がでる
また面接の内容に一貫性がでる、というメリットもあります。就活生に多い悩みの1つが「ガクチカ・自己PR・志望動機の一貫性がない」という点です。
この悩みを、就活の軸を決めることで解決できる可能性があります。
例えば、
・人とコミュニケーションが取れる
・裁量権が大きい
という2つの軸を決めたとします。
面接官は「なぜその2つを軸としたのか」と聞いてくるでしょう。
その問いに対し、「学生時代に長期インターンシップで、インターンリーダーを務めた経験から、裁量権が大きい環境であるほど、自身のモチベーションが上がることが分かったからです」などと答えれば、志望動機(就活の軸)とガクチカ・自己PRの一貫性が生まれるはずです。
細かい志望動機を決める前に、「この条件だけは、必ず満たしている企業を受ける」「法人営業ができる会社に行きたい」などと、大まかな就活の軸を決めましょう。
就活の軸を決めた後に、ガクチカ・自己PRでアピールすべき内容を考えることで、一貫性のある面接になるはずです。
メリット3:将来ビジョンが明確になる
例えば「日本が抱える社会問題を解決したい」「ITスキルが活かせる仕事に就きたい」といった軸は、過去の経験と将来やりたいことの両側面から決められた軸といえます。
「何となく就活をやっていた」という人でも、就活の軸を決めることによって、今よりも将来ビジョンが明確になるはずです。 就職活動で人生は終わりません。むしろ就職してからが本番です。
「内定を取るためにどうしたらよいか」だけを考えるのではなく「自分が本当にやりたいことは何か」を真剣に考えることによって、就活の軸にとどまらない「本当の将来ビジョン」が明確になるでしょう。
あなたは大丈夫?就活の軸を答える時の注意点とは!?
上述した通り、就活の軸とは働くにあたって譲れない要素のことです。とはいえ、ESや面接で伝えるときは、伝え方に気をつけなければなりません。
なぜなら、企業は就活の軸を通して、みなさんの志向性と自社の事業が合っているかを確認しているから。この目的に反したり、適切でないことを伝えるべきではありません。以下に、就活の軸として不適切なものを4つ取り上げます。
(1)待遇面の条件は軸にしない
(2)どの企業でも言えるようなことを言わない
(3)「顧客」ではなく「従業員」であることを意識する
(4)根拠のない軸を話さない
1つずつ具体的に見ていきましょう。
(1)待遇面の条件は軸にしない
「給料が良いこと」や「福利厚生が良いこと」といった待遇面に関する事柄は、多くの就活生が気になるところでしょう。しかし、給料や福利厚生が入社したい理由であるというのは、企業が持つ印象は良くありません。
また、給料・福利厚生の両方が整っていたとしても、仕事が合わなければ企業に馴染むことができないでしょう。これだと企業がみなさんを採用した方が良い理由がなくなってしまいます。
(2)どの企業でも言えるようなことを言わない
「私の就活の軸は、成長できる企業であることです」
就活の軸として、上のようなものを話す就活生は少なくありません。しかし、これはNG。なぜなら、成長は、当事者の意識次第でどこでもできるものだからです。
また、「成長」という言葉の定義を自分のなかで確立していなければ、みなさんが仕事をするうえで何を大切にしているかがうまく伝わらない恐れもあります。
上に挙げた2点を心のなかで思っている分には問題ありません。ただし、企業が質問する意図を考えると話すべきでないこともあるので、注意するようにしましょう。
(3)「顧客」ではなく「従業員」であることを意識する
3つ目の注意点として「顧客目線ではなく、従業員目線の軸を伝える」ことです。
有名メーカーを志望する就活生にありがちな軸が
「御社の製品が素晴らしいから」
といった、商品の性能を根拠とした軸です。
このような軸は面接官に「製品が好きなら、お客様のままでいいよ」と思わせてしまいかねません。
就職活動は、その会社に入社して「売上を上げる従業員として働く」ことを目的として行われるものです。
顧客目線の軸ではなく、売上を作る従業員目線で軸を作りましょう。
(4)根拠のない軸を話さない
先ほども触れましたが、就活の軸は、軸それ自体よりも「なぜその軸に決めたのか」が重要です。
例えば理由もなく
「御社に入社して、環境問題に取り組みたい」
という軸を話したとしても、企業側からすると価値観や根本的な想いは十分に伝わってきません。
また就活の軸は、多くの学生で被ることが多いので、説得力のある根拠を話すことで、他の就活生との差別化にも繋げることができます。
「価値観を伝え、他の就活生と差別化する」ためにも、根拠のない軸は話さないようにしましょう。
MatcherでOB訪問して、説得力のある「軸」を作ろう!
今まで就活の軸を見つける方法についてご紹介してきました。所属大学・地域関係なくOB・OG訪問ができるサービスMatcherでは、就活の軸を社会人や内定者と一緒に作っていくことも可能です。

簡単・気軽に、訪問する社会人を見つけて日程調整することができるため、OB訪問が初めての方にもオススメ!納得のいく就活を行うために、ぜひご活用いただけたら嬉しいです。